GX志向型住宅とは?メリット・ZEHとの違い・補助金を分かりやすく解説
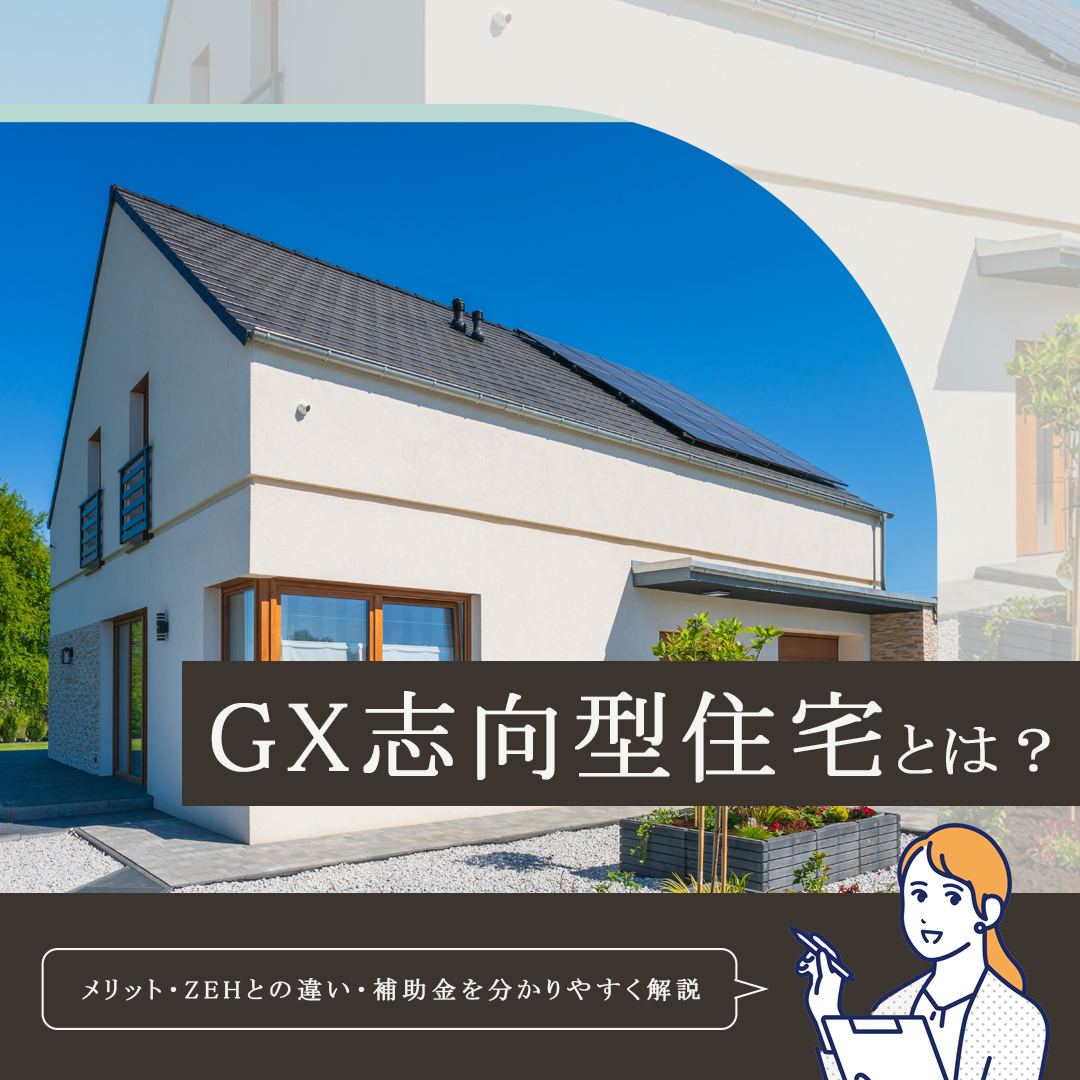
新築住宅を検討している方の多くは、将来の光熱費や環境への配慮、さらには住宅の資産価値について不安を感じているでしょう。この記事では、GX志向型住宅の基本的な仕組みからメリット・デメリット、活用できる補助金制度まで、わかりやすく解説していきます。
GX志向型住宅とはどんな家?
「GX志向型住宅」とは、GX(グリーントランスフォーメーション)の考え方を取り入れた次世代型の省エネ住宅です。高い断熱性能と高効率設備の導入により一次エネルギー消費量を大幅に削減し、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用して、一次エネルギー消費量100%以上の削減を目指します。従来の省エネ住宅の代表格であるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や長期優良住宅よりも厳しい基準が設けられており、2050年カーボンニュートラル実現に向けた政府の重要な政策の一環として位置づけられています。
GX志向型住宅が推進されている背景
日本政府は2050年カーボンニュートラル実現を国際的に約束しており、その達成には、住宅分野でのエネルギー消費削減が不可欠です。建築物のエネルギー消費量は国内全体の約3割を占めており、住宅の省エネ化は環境問題解決の鍵を握っています。
また、エネルギー価格の高騰により家計の光熱費負担が増加している現状も、高性能住宅への需要を後押ししています。大地震など自然災害の頻発により、エネルギー自給能力を持つ住宅の重要性も高まっています。
こうした背景から、政府は2030年度までに新築住宅のZEH基準水準の省エネ性能確保を義務化する方針を掲げ、GX志向型住宅の普及を通じて住宅の省エネ化を加速させています。
GX志向型住宅とZEH・長期優良住宅の違い
省エネ住宅にはさまざまな種類がありますが、GX志向型住宅はそのなかでも最も高い性能基準を持っています。
GX志向型住宅とZEH水準住宅の違い
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指す住宅です。断熱等性能等級5以上、再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率20%以上の基準があります。
一方、GX志向型住宅は断熱等性能等級6以上、再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率35%以上と、より厳しい条件をクリアする必要があります。
GX志向型住宅と長期優良住宅の違い
長期優良住宅は「長期間良好な状態で住み続けられること」を目的とし、耐震性、劣化対策、維持管理・更新の容易性など多岐にわたる基準が設けられています。一方、GX志向型住宅は省エネ性能に特化しており、環境負荷低減に焦点を当てた住宅です。
GX志向型住宅に求められる基準
GX志向型住宅として認定されるためには、4つの重要な要件を満たす必要があります。これらの基準は従来の省エネ住宅よりも厳格で、住宅の設計・施工には高度な技術と知識が求められます。出典:子育てグリーン住宅支援事業公式サイト
断熱性能等級6以上
断熱性能等級6は、ZEH基準(等級5)を大きく上回る高い断熱性能を示します。この基準をクリアすることで、外気温の影響を受けにくく、年間を通じて快適な室温を維持できます。
断熱性能を表す2つの指標丨UA値とηAC値
断熱性能は「UA値(外皮平均熱貫流率)」と「ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)」の2つの指標で評価されます。
UA値は建物全体の断熱性能を示し、数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性が高いことを意味します。断熱等性能等級6では、地域区分5、6、7において、UA値0.46以下が求められます。
ηAC値は夏季の日射熱取得を抑える性能を示し、数値が小さいほど日射遮蔽性が高く、冷房負荷を軽減できます。地域特性に応じて基準値が設定されているため、地域密着型の住宅会社であれば、その地域の気候特性に最適な断熱仕様を提案できるでしょう。
再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を35%以上削減
「住宅そのものの省エネ性能」を評価する基準です。太陽光発電などの創エネ効果を除いた状態で、基準となる一次エネルギー消費量から35%以上の削減が求められます。
具体的には、高断熱・高気密設計、高効率エアコン、エコキュートやエネファームなどの高効率給湯器、LED照明などの導入により実現します。ZEH基準の20%削減と比較すると、15ポイントも高い削減率が要求されており、相当に高度な省エネ技術が必要です。
再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量を100%以上削減
これは「エネルギーの自給自足」を目指す基準で、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを活用して、年間のエネルギー収支をプラスにすることを求めています。つまり、住宅で消費するエネルギーよりも多くのエネルギーを自家発電で生み出す必要があります。
この基準により、光熱費の大幅削減、CO2排出量の削減、災害時のエネルギー確保といった多面的なメリットが得られます。余剰電力の売電収入も期待でき、長期的な経済メリットも大きくなります。
寒冷地や多雪地帯は要件が緩められている
北海道などの寒冷地や多雪地帯では、暖房需要が大きく、日照時間も限られるため、削減率が75%以上に緩和されています。都市部の狭小地では、太陽光パネルの設置面積が制限されるため、再生可能エネルギーの導入要件が除外される場合もあります。
高度エネルギーマネジメント(HEMS)の導入
GX志向型住宅の必須要件として、HEMS(Home Energy Management System)の導入が義務づけられています。具体的には、「ECHONET Lite AIF仕様」に対応するコントローラーとして、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている認証製品を設置する必要があります。
HEMSは住宅のエネルギー使用状況を「見える化」し、家電機器や設備を最適に制御するシステムです。電力の無駄を削減し、省エネ効果を最大化するだけでなく、蓄電池や電気自動車との連携も可能になります。
GX志向型住宅を建てるメリット
GX志向型住宅は初期投資こそ大きくなりますが、長期的に見ると多くのメリットがあります。経済的な効果から健康面、環境への貢献まで、幅広い恩恵を受けることができます。
光熱費を削減できる
高い断熱性能により冷暖房費を大幅に削減し、高効率設備の導入でさらなる省エネを実現します。太陽光発電による自家消費により、電気代をほぼゼロにすることも可能です。光熱費の高騰が続く現在、エネルギー自給率の高い住宅は家計の強い味方となるでしょう。
30年間の住宅ローン期間中に削減できる光熱費は数百万円に達することもあり、初期投資を十分に回収できる計算になります。
環境保護に貢献できる
GX志向型住宅は、一般的な住宅と比較して、CO2排出量を大幅に削減できます。太陽光発電による化石燃料依存度の低減により、環境負荷を最小限に抑えられます。
子どもたちの将来のために、持続可能な社会の実現に貢献したいと考える家庭にとって、こうした住宅は理想的な選択肢といえるでしょう。
快適な住環境を実現できる
高断熱・高気密性能により、室温が一年中安定し、部屋間の温度差も少なくなります。これによりヒートショックや熱中症のリスクが軽減され、健康的で快適な住環境を実現できます。
資産価値が上がりやすい
政府の環境政策強化によって、省エネ性能の高い住宅の市場価値は、今後さらに高まると予想されます。新築時の投資が将来の資産価値向上につながり、売却時や相続時にもメリットを得られる可能性があります。
環境性能が住宅評価の重要な指標となりつつある現在、GX志向型住宅は将来を見据えた賢い投資といえるでしょう。
GX志向型住宅のデメリット・注意点
メリットの多いGX志向型住宅ですが、建築前に理解しておくべきデメリットや注意点もあります。これらを把握したうえで、適切な対策を講じましょう。対応できるハウスメーカーが限られる
GX志向型住宅は高度な設計力・施工力が求められるため、対応できる住宅会社は限られています。具体的には、ZEHやHEAT20 G2/G3といった、高性能住宅の施工実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。
実績の少ない会社に依頼すると、設計に不備があったり施工品質が低かったりして、期待した性能を得られないリスクがあります。
初期コストが高くなる
高性能断熱材、再生可能エネルギー設備、HEMS、高効率設備などの導入により、初期費用は一般的な住宅よりも高くなります。
地域によっては太陽光発電の効率が落ちる
太陽光発電システムの効果は、日照条件や設置条件により大きく左右されます。たとえば、北向きの屋根や周囲に高い建物がある場合、期待した発電量を得られない可能性があります。
立地条件によっては対象外になる
危険性が高いと思われる立地に建てられた場合、GX志向型住宅の対象外となる場合があります。
土砂災害特別警戒区域
災害危険区域
市街化調整区域内の特定のエリア
さらに、床面積の指定(50㎡以上240㎡以下)から外れた住宅も同じく対象外となります。土地探しの段階から、これらの条件を考慮したうえで計画を立てましょう。
GX志向型住宅で活用できる補助金
GX志向型住宅の初期コストの高さは、各種補助金制度を活用することで大幅に軽減できます。主要な制度について詳しく見ていきましょう。子育てグリーン住宅支援事業
GX志向型住宅の最も重要な補助金制度が「子育てグリーン住宅支援事業」です。この制度は、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、高性能住宅の普及を支援する政府の重要政策として位置づけられています。
経済産業省、国土交通省、環境省が連携して実施する、信頼性の高い制度です。「子育てエコホーム支援事業」の後継として、2025年からスタートしています。
対象となる住宅の要件
GX志向型住宅として補助金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
断熱等性能等級6以上
再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率35%以上
再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率100%以上(寒冷地等は75%以上)
HEMS設置
床面積50㎡以上240㎡以下
2024年11月22日以降に工事着手
グリーン住宅支援事業者による施工
GX志向型住宅はすべての世帯が対象となり、1戸あたり160万円の補助金を受けられます。(予算上限額に達したため、2025年給付分は7月22日に受付終了しています)
これは長期優良住宅の80万円、ZEH水準住宅の40万円と比較して、最も高い補助額です。
申請方法
申請は原則として施工会社(グリーン住宅支援事業者)が代理で行うため、施主自身が複雑な手続きを行う必要はありません。
ただし、交付申請の予約と交付申請の2段階の手続きがあるため、スケジュール管理が重要です。施工会社が事業者登録を完了しているか、必ず確認しておきましょう。
給湯省エネ2025事業
エネルギー消費効率の高い給湯器の設置を支援する制度です。エコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファームなどが対象となり、補助金額は6〜20万円程度です。
GX志向型住宅では高効率給湯器の導入が重要な要素となるため、この制度の活用も検討価値があります。
先進的窓リノベ2025事業
既存住宅の窓の断熱改修を支援する制度で、複層ガラスや内窓設置などが対象となります。新築のGX志向型住宅では基本的に対象外ですが、リフォーム時には有効活用できます。
補助金の注意点
補助金制度を活用する際は、以下の点に注意が必要です。
補助金の併用は不可能(例外あり)
原則として、国費が充当されている他の国の補助制度との併用はできません。具体的には、子育てグリーン住宅支援事業の新築補助金と、先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業は同一住宅では併用不可です。
ただし、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されていない限り併用可能です。また、蓄電池のDR対応補助金は併用できる場合があります。
出典:子育てグリーン住宅支援事業公式サイト
予算に到達すると受付が終了する
補助金には予算上限があり、予算に達し次第受付が終了します。過去の類似事業でも、申請開始から数か月で予算満了となるケースが多いため、早期の申請準備が推奨されます。
の申請準備が推 GX志向型住宅を建てる際のチェックポイント
GX志向型住宅を建てる際は、以下のポイントを重視して進めることで、後悔のない家づくりを実現できます。GX対応の実績が豊富な施工業者を選ぶ
GX志向型住宅の建築には、高い設計力・施工力が求められます。ZEHやHEAT20 G2/G3などの環境配慮型住宅の施工実績が豊富なハウスメーカーや工務店を選ぶことが成功の鍵となります。
実績豊富な住宅会社であれば、地域の気候特性を活かした最適な仕様提案から、施工品質の確保まで、安心して任せることができるでしょう。
補助金や税制に詳しい担当者に付いてもらう
補助金制度や税金の優遇制度は複雑で変更も多いため、専門知識を持った担当者のサポートが不可欠です。資金計画や住宅ローン、補助金などの相談に対応し、個別のFP相談も提供している住宅会社であれば、お客様の経済状況に最適化された資金計画を提案してもらえるでしょう。
購入後のサポート体制もチェックしておく
GX志向型住宅では太陽光発電システムやHEMSなど、高度な設備が多数導入されます。これらの設備は定期的なメンテナンスが必要で、長期的なサポート体制が重要になります。
アフターサービスの充実度や保証内容、メンテナンスコストなどを事前に確認し、長期的な安心感を提供できる体制があるかを見極めましょう。
初期費用とランニングコストを踏まえた予算管理・返済計画を立てる
GX志向型住宅は初期費用が高くなる傾向にありますが、光熱費削減効果や資産価値向上により、長期的なトータルコストで判断することが重要です。
30年間の住宅ローン期間中の光熱費削減効果、補助金の活用効果、将来の売却価値なども含めて、総合的な経済性を評価しましょう。
太陽光発電の効率を考えた設計を考える
太陽光発電システムの効果を最大化するためには、屋根の向きや角度、年間発電量の期待値、蓄電池との組み合わせなど、設計段階からの検討が重要です。
土地探しからサポートしている住宅会社であれば、太陽光発電に有利な立地条件も考慮した土地選びから、最適なシステム設計まで、トータルでサポートしてもらえます。
まとめ
GX志向型住宅は、ZEHを大きく上回る省エネ性能で環境負荷を大幅に削減し、エネルギーの自給自足を実現する次世代型住宅です。断熱等性能等級6以上、一次エネルギー消費量35%削減、再生可能エネルギー活用による100%削減、HEMS導入という4つの厳しい基準をクリアすることで、光熱費の大幅削減、快適な住環境、資産価値向上といった多面的なメリットを得られます。
辰巳住宅では、地域密着型の強みを活かし、3,500棟以上の豊富な施工実績と高気密高断熱住宅へのこだわりで、お客様の理想のGX志向型住宅を実現します。土地探しからご入居後まで一貫したワンストップサポートにより、安心の家づくりをお約束いたします。
辰巳住宅では、注文住宅でこだわりの家づくりを実現できます。詳しくはこちらをご覧ください。
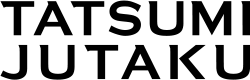


 0120-30-2501
0120-30-2501


